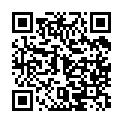ばね力学用語(2) 弾性係数とは
ばねの設計をするときに、応力-ひずみ線図とか材料の引張強さの話が出てきます。降伏点、耐力、縦弾性係数に横弾性係数、ポアソン比など、何のことやらサッパリわからない用語がたくさん出てきます。
これらは、ばねを設計するときに必要なものなのですが、どのように必要なのかを順を追って説明します。
ばね力学用語(1)では、ばね定数について説明しました。ばね定数の基本計算式は、次のようになります。(どうして、このような式になるのかは、また別の機会に説明します。)
「ばね定数=(横弾性係数×線径4)÷(8×有効巻数×コイル中心径3)」
さて、この式からわかることは、
1.ばね定数は、①線径 ②有効巻数 ③コイル中心径という3つのパラメーター(変数)によって定まる。
2.横弾性係数という、ある一定の数が関係している。
ということです。
では、この横弾性係数とはどういう数なのでしょうか。横弾性係数は剛性率ともいいます。また、縦弾性係数というのもあります。こちらは、ヤング率ともいわれています。説明するのには、縦弾性係数(ヤング率)のほうがわかりやすいので、まずこちらから説明します。
ヤングというのは、人物の名前です。トーマス・ヤング(1773~1829)はイギリスの医者で物理学者です。「エネルギー」という言葉を創りだし、最初に使用した人としても有名です。
ヤング率とは、「フックの法則が成立する弾性範囲における、同軸方向のひずみと応力の比例定数である」(ウィキペディア)とされます。
この定義には、
①フックの法則 ②弾性 ③ひずみ ④応力 という言葉が出てきます。これらの言葉とヤング率について順に説明していきます。
①フックの法則とヤング率
フックの法則を押ばねに適用した場合については、「ばね力学用語(1)-ばね定数とは」で説明しました。フックの法則というのは、押しばねに適用できるだけでなく、金属の線材そのものにも適用できます。ある一定の力で線材を引っ張ると(ものすごい力ですが)、線材は伸びます。そのときの力と伸びは比例の関係になります(Y=aXという式になります)。このaという係数は、金属ごとに異なっていますが、同じ材料ならば一定の値となります。この比例定数aをヤング率といいます。記号ではEと表示します。材料における「ばね定数」です。
②弾性とヤング率
弾性とは、そもそもどういう意味でしょうか。弾性の反対は塑性といいます。
簡単にいうと、材料を引っ張っていた力を抜いたとき、元の形状にもどる場合を弾性といいます。元に戻らずに変形したままになってしまう場合を塑性といいます。ヤング率は弾性のときの性質で、力を入れすぎて形状が元に戻らなくなってしまったときには成立しません。これが弾性の範囲内という意味です。
縦弾性係数(ヤング率)は引張り方向についての性質だと理解していいと思います。横弾性係数は、ねじり方向に変化させる場合をいいます。ねじった場合の変化も弾性の範囲で比例の関係となり、これも材料ごとに一定の値となります。
なんとなく、横弾性係数をイメージしていただけたでしょうか?横弾性係数は記号ではGと表示します。
これまで、ひずみのことを「伸び」、応力のことを「力」と簡単にいって説明してきました。
「応力」と「ひずみ」という概念は、簡単なようで難しいところがあります。ガリレオ・ガリレイ(1564~1642)も材料の応力について研究した物理学者でしたが、実用に使えるような設計・計算式に到達することはできませんでした。
では、③ひずみ と ④応力 とは、どのような概念なのでしょうか・・・
(つづく)
>YouTubeチャンネル【ばねの総合メーカー「フセハツ工業」】動画配信中です!
>新YouTubeチャンネル【フセハツ工業のばね作りチャンネル】新着製造動画、更新中です!
■ばね用語に関連する項目
プロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の公式スポンサーになりました!
>ブログ「ばねとくらす」【プロバスケットボールチームの公式スポンサーになりました】
 |
メールアドレスはこちら
![]()