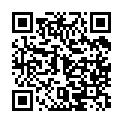ばね力学用語(1) ばね定数とは
ばねの設計をするときに、応力-ひずみ線図とか材料の引張強さの話が出てきます。降伏点、耐力、縦弾性係数に横弾性係数、ポアソン比など、何のことやらサッパリわからない用語がたくさん出てきます。
これらは、ばねを設計するときに必要なものなのですが、どのように必要なのかを順を追って説明します。
はじめに、ばね定数についてです。
話をわかりやすくするために、押しばねを設計するときを例にとって説明します。
例えば10mm押さえて、100Nの荷重が欲しいときには、ばね定数10N/mmのばねを作ればよいことになります。ばね定数とは1mm押さえるのに必要な力をいいます。ばね定数が大きければ、少しくらい押しても変形しません。逆に、小さければフワフワのばねになります。
数式でいうと、
「荷重=変形量×ばね定数」 となります。いわゆるフックの法則です。
ロバート・フック(1635~1703)はイギリスの自然哲学者です。今でいうと科学者です。フックはこの法則の成果として、ばねを使って懐中時計を発明しています。それまでは大きな振り子時計しかありませんでした。
また、顕微鏡観察から生物の最小単位を「細胞」とした最初の人でもあります。「イギリスのレオナルド・ダ・ヴィンチ」ともいわれましたが、ライバルのニュートンの影にかくれてしまい、功績が評価されなくなった面があります。
さて、ばね定数に話を戻します。
次に、ばね定数が10N/mmにするには、どのような線径がいいのか、コイル中心径はどうするのか、また、有効巻数をどうするのかを決める必要があります。この3つの要素がばね定数すなわちばねの力を決めています。
ばね定数を決める3つの要素
①線径 ②コイル中心径 ③有効巻数
一般的な傾向として、
線径が大きいほど、ばね定数は大きくなります。つまりカタイばねになります。
コイル中心径が大きいほど、ばね定数は小さくなり、フワフワのばねになります。
有効巻数が多いほど、ばね定数は小さくなり、フワフワのばねになります。
この3つの要素を当てずっぽうに組み合わせて、ばねの試作を何回も闇雲にやってもなかなか狙ったばね定数は出ません。時間ばかりかかってしまいます。少なくとも産業革命まではこのような行き当たりバッタリの方法でばねが設計されていました。
そこで、もっと効率よくばねを設計できる何かよい方法はないのかということで、この3つの要素の関係が長年にわたり研究されてきました。その結果、ある法則に従ってこの3つの要素は、ばね定数に関係していることがわかりました。
その法則とは
「ばね定数=(横弾性係数×線径4)÷(8×有効巻数×コイル中心径3)」 というものでした。
ここに、横弾性係数という新しい項目が登場してきます。これは一体何なのか。
(つづく)
■ばね用語に関連する項目
>YouTubeチャンネル【ばねの総合メーカー「フセハツ工業」】動画配信中です!
>新YouTubeチャンネル【フセハツ工業のばね作りチャンネル】新着製造動画、更新中です!
プロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」の公式スポンサーになりました!
>ブログ「ばねとくらす」【プロバスケットボールチームの公式スポンサーになりました】
 |
メールアドレスはこちら
![]()